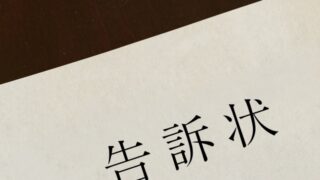刑事告訴は、よく聞く言葉かもしれませんが、実際の手続となると、何をどのように記載すればよいのか、決まった形式はあるのか、などわからないことばかりだと思います。
加えて、被害届とは違い、刑事告訴は、弁護士や行政書士が作成したものであってもなかなか受理されないケースは多くあります。
しかし、スムーズな受理に至るためにも、法的に整理された内容を記載することが大きなポイントとなります。
そこで、一般的な告訴状には、何をどう記載するのかなど告訴状の書き方についてご紹介したいと思います。
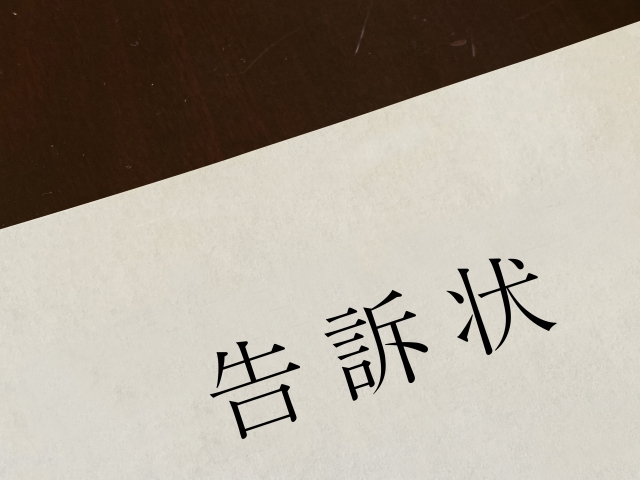
まず最初に、「告訴状に決まった書式はないのかな」、「ネットを検索してみたけれど、サイトによって微妙に異なり、統一されていない?」と思うかもしれません。
その通り、告訴状に決まった書式はありません。極端に言えば、どこに何を、どういう順番で記載するかは自由です。
しかし、実務上は、ある程度のスタイルは確立されつつあり、それに従って告訴状を記載するのがベターといえるでしょう。その上で、ケースや必要に応じて、適宜告訴状の内容や形式に変更を加えていきます。
告訴状の記載内容
一般的な告訴状の記載内容は次の通りです。
・タイトル
・日付
・宛先
・告訴人名
・被告訴人名
・告訴の趣旨
・罪名及び罰条
・告訴事実
・告訴に至る経緯及び関連事情
・立証方法
タイトルはもちろん、「告訴状」です。告発であれば「告発状」になります。
日付は基本的に警察署に持参する日を記載しますが、持参してもその日に受理されないケースが多いことを考えると、日にちだけ空欄にしておき(月をまたぐ可能性がある場合は月も)、正式受理となればその場で、又は対応した警察の指示で、日にちを記載する対応で良いでしょう。
宛先は、持参提出先の警察署です。都道府県によって記載内容が異なります。例えば、東京都内の警察署であれば「警視庁●警察署署長」、北海道であれば「北海道●方面●警察署署長」、大阪京都であれば「●府警●警察署署長」、その他県であれば「●県●警察署署長」となります。なお、告訴又は告発は検察庁に対してもできますが、検察庁宛の告訴又は告発は行政書士の業務範囲外ですので、もし検察庁に提出したい場合は弁護士又は司法書士にご相談ください。
告訴をする人の名前と住所、生年月日を記載し、押印(認印で可)します。警察署や対応した警察官によって異なりますが、告訴人名を自署で求められることがあります。源氏名や芸名など通称名がある場合は、「●こと(本名)」と記載するのが一般的です。
令和7年5月23日、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し(令和9年3月31日までに全面的に施行予定)、告訴状又は告発状に記載しなければならない項目として規定が新設されました。
その内の一つが、「告訴又は告発をする者の氏名及び住所又はこれに代わる連絡先(法人にあっては、その名称又は商号、代表者の氏名及び主たる事務所又は本店の所在地)」です。
つまり、告訴又は告発をする者は、その氏名、住所を記載するか、住所に代わる連絡先(電話番号など)を記載しなければなりません。ただ、改正法は令和9年3月31日までに施行される予定で、令和7年6月時点では改正法は適用となりません。
告訴状の記載内容に関して、よくある疑問の一つです。ネット上の名誉毀損などは、誹謗中傷の投稿をした者の氏名は全く不明であることがほとんどです。その場合でも告訴できるのかという点ですが、氏名不詳者であっても告訴することはできます。ネット上の誹謗中傷(名誉毀損)は別として、被告訴人に関してわかっている情報があれば可能な限り記載した方が受理後の捜査に役立てることができます。
刑事告訴は、捜査機関に対して犯罪被害に遭った事実を申告するのみならず、犯人に対して処罰を求める意思表示も含まれます。そして、この意思表示は、告訴の趣旨で明らかにします。先ほどご紹介した改正法でも、「その犯人の処罰を求める旨」は告訴状又は告発状に記載することになっています。
例えば、名誉毀損罪(刑法230条1項)で刑事告訴するケースで、
ごく簡潔に記載するならば、
「被告訴人の下記所為は、刑法第230条(名誉毀損罪)に該当するものであるので、被告訴人に対する厳重な処罰をされたく告訴する。」となり、
要点的に記載するならば、
「被告訴人は、令和7年●月●日頃、インターネット上のサイト●で、「●」などと投稿し、これを不特定かつ多数の者に閲覧させ、もって公然と事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損したものである。」となります。
どちらも間違いではないので、お好みで良いと思います。なお、後者の文言で告訴の趣旨を記載した場合は、後述する告訴事実の締め(結論)で、「以上、被告訴人の上記行為は、刑法第230条(名誉毀損罪)に該当するものであるので、被告訴人に対する厳重な処罰をされたく告訴する。」と記載しておくと良いでしょう。
罪名及び罰条に関しては、告訴の趣旨でも記載しているので、特段記載する必要はありませんが、複数の罪(例えば名誉毀損罪と脅迫罪)で刑事告訴する場合には、警察が一目で何の罪で刑事告訴しようとしているのかわかるように記載しておいた方が親切です。
告訴状において、最も重要であり、かつ難しい記載項目です。
各犯罪には、成立するための条件(構成要件と言います。)があり、これを満たさなければ犯罪として成立しません。基本的に、構成要件は条文から導き出され、例えば、名誉毀損罪(刑法230条1項)であれば、条文が「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」であり、構成要件は、①公然、②事実を摘示、③名誉を毀損、となります。
告訴事実を記載する際のポイントは、時系列に沿って、被告訴人のどういう行為が名誉毀損罪の構成要件があてはまるのか、を理路整然と記載しなければなりません。そこに、告訴人の感想、憶測・推測は必要ありません。余計な情報は記載せず、事実のみを告訴事実に記載するようにしましょう。事件の背景として必要な部分は、次に紹介する告訴に至る経緯や関連事情で記載しましょう。
事件の背景として必要であれば記載します。特に無ければ、記載するどころか、項目として設ける必要もありません。
ここは証拠です。ネットのフォーマット、弁護士、行政書士、司法書士によってマチマチですが、弊所では「弁第●号証」として証拠のタイトルを記載し、告訴事実で「弁●」などとして引用することが多いです。証拠については多ければ多いほど良いというわけではなく、告訴状作成の段階において適当な証拠が揃っていれば一先ず十分です。警察から追加の証拠提出を求められることがありますが、その都度対応していくことになるでしょう。
ここまで告訴状に記載する一般的な項目について解説しました。
ただし、告訴状又は告発状に記載してはならないことがあります。それは、犯人に対する処罰を求める意思表示が曖昧になる記載です。例えば、「被告訴人から示談の申入れがあった場合は和解に応じる意向である。」などです。確かに、刑事告訴が受理されると、捜査機関に捜査開始義務が生じ、捜査の結果、被告訴人を逮捕することがあります。被告訴人(犯人)が最終的に不起訴処分を獲得するためには示談成立が必要不可欠となり、被告訴人から(正確には弁護人から)示談の申入れがなされることがあります。もちろん結果的に示談に応じることは問題ないのですが、告訴する段階で、示談に応じる用意があると明言してしまうと、人員を割いて捜査に当たる捜査機関としては、「犯人に処罰を求めるんじゃないの?最初から示談に応じるつもりなら、そのために我々警察を利用するようなものじゃん。」となって、まず受理されないでしょう。
他にも、言葉の定義的な説明は要りません。告訴状は論文などではないので、どういう被害事実があったのかを記載すれば事足ります。
今回は、告訴状に何を記載したら良いのか、又は何を記載したらいけないのか、を中心に解説しました。特に、告訴事実は告訴にあたっては非常に重要で難しいところです。告訴状の作成には専門家のサポートが必要となるケースもあるでしょう。
当事務所では、告訴状又は告発状の作成依頼を受け付けております。行政書士に依頼したからと言って、必ずしも受理されるわけではありませんが、スムーズに受理されるような告訴状を作成することができます。もっとも警察署に持参提出した場合でも(郵送不可)、その場で受理されることはほとんどなく、訂正や追加の証拠を求められることが多いです。当事務所では、告訴状又は告発状作成のご依頼後、警察から訂正や修正を求められた場合のアフターサポートもお受けすることもできますので(要相談)、お悩みの方はお気軽にご相談ください。